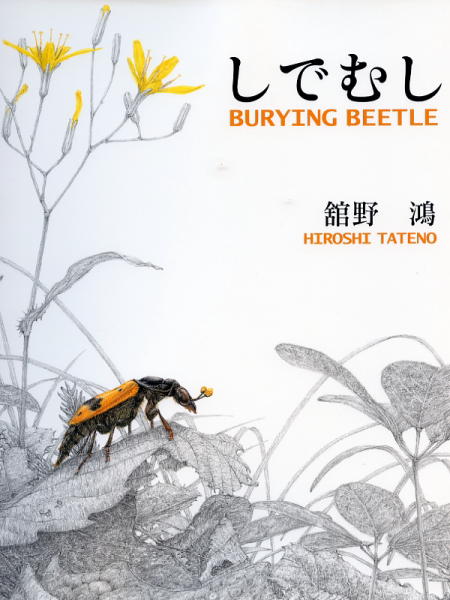[ 宮崎県 三股町 ]
今朝も我が家の林で、ウグイスの綺麗な囀りを聴いた。
ウグイスは人に聴かせるために囀っているのではない、という生物学的な
視点も必要かと思う。でないと、ウグイスを籠に入れて飼い慣らすという
趣味に走る人もあり、籠のなかのウグイスは哀れである。
昨日、犬の散歩中に偶然見つけたナガサキアゲハの越冬蛹はコナラの
小木についていた。地面から30センチ程の低い位置にある。だから見落としていた。
 この蛹が育ったミカンの木は一番近くでも10メートルは離れている。長旅、ご苦労様。
この蛹が育ったミカンの木は一番近くでも10メートルは離れている。長旅、ご苦労様。
でもこの梢でこの鮮やかな緑色とは、ちょっと怪しい。
残念ながら、寄生されているかもしれない。
ナガサキアゲハ越冬蛹を撮影してから立ち上がり、ふと上空を見上げれば、
ウスタビガ♀の繭殻があった。 え!こんなところに!?
 繭には卵が4個付いている。
繭には卵が4個付いている。
このコナラの木には、別に♂の繭殻も以前に見つけてあったが、この♀の繭殻はまったく
死角にあって今日まで気付か無かった。
振り返ってみれば、我が家の林では去年、ウスタビガの発生が多かったと言えるだろう。
今日は東京から仕事でお客さんがみえた。
宮崎空港からうちに戻る途中、田野町の宮崎大学演習林に立ち寄り、林道をあるいてみた。
ビロードツリアブ、ルリタテハ、キタテハ、キチョウ、モンシロチョウ、ルリシジミ、
ホソミオツネントンボ、ホソミイトトンボ、タイワンツノアブラムシなど、昆虫の姿も
そこそこあって、獣のフィールドサインもいくつか見つかり楽しいフィールド歩きができた。
今朝も我が家の林で、ウグイスの綺麗な囀りを聴いた。
ウグイスは人に聴かせるために囀っているのではない、という生物学的な
視点も必要かと思う。でないと、ウグイスを籠に入れて飼い慣らすという
趣味に走る人もあり、籠のなかのウグイスは哀れである。
昨日、犬の散歩中に偶然見つけたナガサキアゲハの越冬蛹はコナラの
小木についていた。地面から30センチ程の低い位置にある。だから見落としていた。
でもこの梢でこの鮮やかな緑色とは、ちょっと怪しい。
残念ながら、寄生されているかもしれない。
ナガサキアゲハ越冬蛹を撮影してから立ち上がり、ふと上空を見上げれば、
ウスタビガ♀の繭殻があった。 え!こんなところに!?
このコナラの木には、別に♂の繭殻も以前に見つけてあったが、この♀の繭殻はまったく
死角にあって今日まで気付か無かった。
振り返ってみれば、我が家の林では去年、ウスタビガの発生が多かったと言えるだろう。
今日は東京から仕事でお客さんがみえた。
宮崎空港からうちに戻る途中、田野町の宮崎大学演習林に立ち寄り、林道をあるいてみた。
ビロードツリアブ、ルリタテハ、キタテハ、キチョウ、モンシロチョウ、ルリシジミ、
ホソミオツネントンボ、ホソミイトトンボ、タイワンツノアブラムシなど、昆虫の姿も
そこそこあって、獣のフィールドサインもいくつか見つかり楽しいフィールド歩きができた。